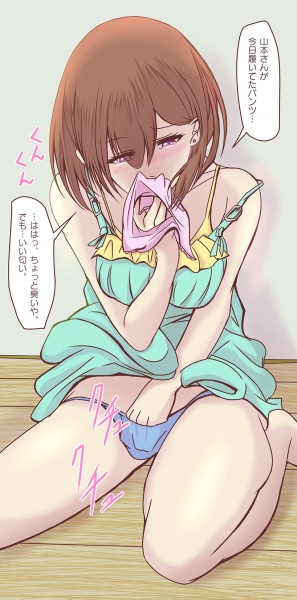とある高校の生徒指導室にて、俺は頭を悩ませていた。
俺の名は藤沢。今年教師になったばかりで生徒指導担当となったのだが、温厚そうな顔かつ声に迫力もないため、生徒が言うことを聞いてくれないというのが悩みだ。
今日も非行に及んでいるという生徒を呼び出し、噂を確かめようとしたのだが訪れる気配はない。
時刻は既に18時を回っている。12月の初頭ともなればもう外は真っ暗で、野球部のナイター設備が稼働しているほどだ。
「もう来ないな……一応教室まで行ってみるか」
俺は今日呼び出した生徒のクラスまで向かってみるが、そのフロアからして電気がついていない。すぐに回れ右をした。
その途中、ボールペンのインクが切れていることを思い出した俺は、教師持ち出し自由の文房具置き場がある物置に寄る。
そこで替えのボールペンを貰い、部屋を出ようとすると何かを踏んづけた。
「……ん? これは……出席簿?」
足蹴にしたものは『欠席者が出ない出席簿』と書かれた黒いボール紙製の小冊子だった。開いてみると、横軸に日付、縦軸に名前を記述するという出席簿の体をなしている。
「欠席者が出ない……か」
今日の事を思い返す。書くだけで欠席がなくななら、これほど便利なものはないと失笑しつつ、ちょっとした願掛け程度のつもりで、俺はその出席簿を持ち出した。未使用のようだし構わないだろう。
「さて、続きをやるか……」
職員室に到着した俺は、書類仕事を再開する。その時出席簿をファイルと書類の山に紛れ込ませてしまい、その日は思い出すことなく終えたのだった。
翌日。俺は校門近くで出入りする生徒達を見守っていた。風紀がどうと口うるさく言うつもりはない。担任も担当教科もない俺が、生徒とのコミュニケーションを図るためだ。
そこそこに挨拶をくれる生徒たちを迎える中に、俺は一人の女子生徒を見つけた。
赤茶けたショートヘアに、ブレザーのスカートは短くブラウスは第二ボタンまで留まっていない、見るからにギャルといった様相の生徒だ。
彼女は2年生の内藤 華凛(かりん)。昨日呼び出していた生徒だ。
(普通に出席しているのはいいが……)
俺はゆっくりと華凛へと近づいていき、声をかける。
「おはよう、華凛」
「あ、藤沢先生……おはよーございまーす」
「昨日、放課後来なかったから少し心配していたが元気そうだな」
「すみませーん、ちょっと用事ができちゃって」
華凛は悪びれることなく、返事をする。
「ならしょうがないか。今日は大丈夫か?」
「んー……ちょっとわかんないです」
「来れたらでいい。生徒指導室に少し寄ってくれ」
「はーい……あ、いった! こら、くるみ!」
登校してきた友人に頭をはたかれた華凛は、俺との会話を一方的に切り上げ小走りで去っていった。
(来ないなぁ……あれは)
染めたような頭髪の色や、化粧っぽい肌などあからさまな外見、そこから来る援助交際などの噂。教師を邪険に扱うのは華凛に限った話ではないが、やはり不遜には違いない。
正直に答えてくれるほど信頼関係はないだろうが、体裁もあるので一度はしっかりと話したいというのが俺の考えだった。
(来てくれるのを待つしかないか……)
放課後、すぐ捕まえにいく真似もしたくない。俺はあまり期待はせず待つことにしたのだった。
昼休みを控えた、4時限目。職員室の自席で雑務をこなしている時、ファイル類に出席簿が紛れているのを見つける。
昨日手に入れた『欠席者が出ない出席簿』だ。
「これ……そうだ」
ふと思いつく。今日の放課後の呼び出した華凛をここに書いてやれば、来るのだろうかと。
「2-D 内藤 華凛……っと」
これでよし。
ちょっとしたおまじない、そのつもりで出席簿を閉じて――
――世界が揺れたような、奇妙な感覚に襲われる。
「……?」
スライドのように切り替わった視界は、黒板に板書する教師、周囲の生徒たち、真正面にはブレザーを着た女子生徒の後ろ姿。
ここは教室で、俺は生徒のように席についているようだ。しかしいつの間に? 俺は職員室に居たはずだが。何が起きた。
「ん?」
俺の眼下にある机は、真面目に授業を受けているかのよう。
数学の教科書、丸っこい文字が書かれたノート、ピンク色のペンケース。白いシャープペンシルを握っている指は白く細い。
さらに視線を降ろしていって、俺は言葉を失う。
なんと俺は女子生徒のブレザーを着ていて、胸には膨らみがあったのだ。チェック柄のスカートもしっかり穿いていて、そこから伸びる太ももはムダ毛がなくむっちりとしている。
これじゃあまるで、女子じゃないか。思わず胸に触れると、ふんわりとした感触がてのひらに広がり、男ならありえない位置に触感が与えられた。スカートの上から股間を撫でてみるが、男のチンポの存在感はない。
どういう……ことだ?
「華凛ちゃん華凛ちゃん、どうしたの?」
硬直していると、背中をとんとんと叩かれると同時に女子生徒の声。
華凛、だと? それが俺を呼んでいるのは間違いないが、俺は華凛などという名前では――いや、俺は……華凛?
「べっつにー。なんとなく」
口がひとりでに返事をする。
そうだ、俺……あたしは内藤 華凛。ここで授業を受けるのは当たり前じゃん。どうしていきなり、あたしが藤沢だなんて。昨日ぶっちしたのは、ちょっと悪いと思ってるけど尾を引きすぎじゃない……ん?
(……いや、違う)
混乱しつつも、俺は藤沢という男性教師で、華凛という女子生徒ではないことを思い出す。混じり合い、混濁していた自己認識が水と油のように分離していった。
どうしてと考えたが、思い当たるふしはひとつしかない。
まさか、あの『欠席者が出ない出席簿』が原因か? 俺自身が呼び出した生徒に乗り移ってしまえば、出席はできる。
仮にそうだとして、元の俺はどうなっているんだろうか。
思考を巡らせているうちにチャイムが鳴り、授業が終わる。話しかけてくる女子生徒は無視し、職員室へと駆け出した。
その途中、廊下で徒指導の藤沢……俺が、他の教師と談笑していた。ふらふらと近づいていくと――
俺は華凛の前で、初老の男性教師と話していた。
「――あまり得意ではないですね。藤沢先生は大丈夫なんですか?」
「あ……」
浅黒く太い腕の、俺の身体に戻っている。それに……この教師と話していたのは、甘いものの話?
「……私もですね。この歳だと、チョコとかは全然……」
「ですよねえ」
適当に相槌を打ちつつ、前にいた華凛を見やる。少しの間ぼんやりとしていたようだが、俺と目が合うと引きつった笑いを浮かべた。
「お、おお華凛じゃないか。どうした?」
「んー……なんか、藤沢先生いんのかなと思って」
「そりゃあいるよ」
「なんだろ、あたしもよくわかんないけど。じゃーね」
「おう。放課後来てくれよ」
「行けたら行く~」
話を終えると、俺も男性教師と会釈して別れ一人になる。
なんだったんだ、今までのは。狐につままれた気分だったが、職員室の自席に戻り、手がかりがないか出席簿をもう一度開いてみる。
すると、最後のページには効果らしき内容が書かれていた。
曰く、この出席簿に他人の名前を書けば、その人間に乗り移り自在に操ることができる。行動だけではなく、乗り移った人間の記憶や思考にも影響を与え、どんな不真面目な生徒でも更生させられる。また、元の自分も間違いなくあなた自身として行動しており、戻った時にも記憶は残されている。
これらの効果によって、欠席者を出さない道具……らしい。
俺が華凛になり華凛の記憶を読めたのも、俺が華凛だった間に元の俺が過ごした記憶があるのも、華凛が自分から俺に会いに来たと思っていたのも、すべてこの不思議な出席簿の能力。
最後には、華凛になった俺が元の俺と出会ったことにより『出席』扱いとなって能力が終わった。
そういうことか? 見返してみると、出席簿の華凛のところには丸がついている。書き込んだ記憶ははないが、これも出席簿の能力が終わったことを示しているのか。
これは――現実なのか?
俺が華凛という女子高生になっていただなんて。未だ信じられない。こんな魔法のような道具があるのだと恐怖する反面、その能力は実に面白かった。
「……」
確かめるだけ。俺はそう言い訳しつつ、再び華凛の名前を記入した。
一瞬。
意識が途切れ、俺はまた教室に座っている。俺は……あたしは華凛になっていた。
手元には中身がほとんどないお弁当箱、正面にはとても小柄で制服を着ていても小学生高学年くらいにしか見えない友人の、緒方 來弥(くるみ)。
來弥は、あたしとは高校に入ってからだけど一番仲がいい、ちょっと天然というか天真爛漫でおしゃべりが大好きな子だ。
「――だから、お母さんがいっつも卵焼き作るんだけどね、わたしはもっとお砂糖入れてって言ってるのにお父さんがやだって」
「あたしも甘いほうがいいかな~」
華凛と來弥が弁当のおかずについて話していたことを"思い出して"華凛として返事をする。
やはり、本物だ。念を入れて華凛の記憶を辿ってみるが、俺や出席簿の記憶はまったく残っていない。
俺は一気に鳥肌が立つ。ゲームや映像では体験しえない超現実によって、他人を乗っ取る罪悪感や悪魔のような能力への恐怖はあっさりと隅に追いやられた。
俺は高まった興奮を抑えつつ、ちくわの磯辺揚げと白ごはんを口に運んで咀嚼した後、ペットボトルのお茶で喉を潤す。
「そこでさ、出来た卵焼きにお砂糖かけて食べてみたんだけど、なんか全然おいしくなくて――」
俺は來弥の話を聞き流しながら、ご飯を食べる。
……この箸も弁当箱も高校に入ってからずっと華凛が使っていて何百回と口をつけているものだし、食べかけだったちくわの断面についた後も華凛の歯型。ペットボトルだって朝から飲んでいるものだから、蓋の部分は華凛の唾液でべっとりだしお茶にも混じっている。
元の俺だったら間違いなく警察行きの許されざる行為。しかし今はあたしだから、何の問題もない。
俺は華凛の肉体と記憶を奪い、なりすますことにぞくぞくとしていた。
「ごちそうさま~」
「華凛ちゃん食べ終えるのはやーい。ご飯食べるの早い人ってさ、たくさん食べれるっていうけどお腹……胃の大きさは変わらないじゃない?」
「うんごめん、ちょっとお手洗いいくー」
「あ、はーい。いってらっしゃい」
弁当を片付けた俺は、來弥に言い残して席を立つ。來弥ちゃんはかなりおしゃべりが好きなようで、会話の切れ目がない。どこかで無理やり区切るしかなかった。
「……よし」
俺は緊張しつつ、席を立つ。
廊下に出ると、急に身体中の感覚が気になり始める。特に、胸周りのブラジャーは男にはないものだ。スカートも初めてで、冷たい空気が脚からお尻まで纏わりついてくる。これは女子がストッキングやタイツを穿くわけだ。
俺は寒さを覚えながらも、トイレへと歩いていく。今も、周囲からは華凛にしか見えていない――そう実感しながら歩いているだけで、おかしくなりそうだった。
入るのも、男子トイレではない。誰もいない女子トイレに到着した俺は洗面台の鏡に正対し、男ではなく女子高生が鏡に映っているのに改めて感動する。
「はは……俺、華凛になってる……けど」
しかし頭のどこかで、鏡を見たくないと思う気持ちが湧き出る。これが華凛の感情なのだろうか。考えていると、自然と華凛の記憶が蘇ってくる。
赤茶けた髪は地毛で黒く染めてみたことがあるけど、頭皮が負けちゃって駄目だった。化粧も荒れやすい肌を隠すため、ギャルっぽい服装も、いちゃもんつけてくる先生への反抗。あたしだって、もっと普通がよかった。
藤沢だって、きっとわかってくれない。わかるふりして、周りがどうとかいって矯正しようとしてくる。わざわざ会いたくない。
……そうか。華凛も苦労していたのか。華凛が秘めていた苦しみを当人として実感し、俺は反省する。確かに華凛が想像していた通りだった。
今日の放課後、ケアしてやったほうがよさそうだ。
「……それはそれとして、だ」
俺は一度、華凛の嫌な思い出と大人としての感傷を頭から追い出し、気を取り直して鏡を視る。
凛々しい顔つきに、緩い胸元、短いスカート。誰がどう見ても華の女子高生。それが今の俺。
「ふふ……」
顔がにやけ変な笑い声が出てしまうが、その声も顔も女の子のもの。いやらしさはなく、可愛らしい仕草でしかなかった。
女子生徒に手を出すのではない。俺が女子生徒になったのだから、なんの非もない。
俺は最後の良心を押し込めると個室に入り、ブレザーのジャケット、白いブラウス、中の白いTシャツを次々に脱ぎタンクの上に重ねていく。
「おお……」
俺は上半身にブラジャーを着けていた。淡い赤色のスポーツタイプでゴムが黒色という派手めな色彩が、俺のCカップをしっかりと包み込んでくれている。
運動するわけでもないのに……と思うと、また華凛の記憶から理由が引き出される。
「普通のレースとかポリエステルのだと、ち〜っとちくちくしちゃって。あたし、頭もそうだけど肌あんまり強くないから金具でかぶれたり。だから、こっち……下も、綿のやつがいいんだよね」
華凛として述懐しながら、俺は自然とスカートをたくしあげる。口をついて出たセリフの通り、ショーツも装飾のない綿のスポーツショーツ。
当然、こちらにはチンポの膨らみなどない。
「あ……おしっこしたい……かも」
そんなことをして楽しんでいると、下半身に圧迫感を覚える。男とは少し感覚が違うが、華凛の記憶が尿意だと教えてくれた。
「……え、えへへ……しょーがないよね、おしっこしたいんだもん」
華凛が溜めていたおしっこを、俺が勝手に排泄する。通常ならどうやってもありえない行為に、身体が熱くなる。
おしっこをするためには、華凛のおまんこを見たり触れたりしなければないというのもまた、俺を興奮させた。
「じゃ、じゃあ脱ぐね」
俺はスカートの中に手を入れ、ショーツを下ろす。おまんこからクロッチが離れると、ひんやりとした空気が通った。
「わ……華凛の……あそこ……」
華凛の陰毛はまだ細く真っ直ぐで、土手にぺったりと貼り付くように生える苔のような感じだった。女子高生とはいえまだ成長途上だ。俺の彼女のような、太い縮れ毛が茂っていたそれとは違う。
おまんこの中もじっくり見ようとしたが、それより尿意が勝った。俺は便座に座り直すと、華凛の記憶に従ってお腹あたりの力を抜いていく。
「ひぃ……あっ♡」
下腹部に集中させていた神経が、おまんこのすぐそばに通った尿道の弛緩まで感知する。小さな穴を押し拡げおしっこが出ていき、ぼじょぼじょと下品な音を立てて便器の水を打ち付けていった。
「なにこれ……気持ちいい……っ♡」
排泄は多かれ少なかれ快感を伴うのは、男も同じだ。しかし俺の欲情のせいか、快感の大きさは全く違う。
「んっ……おしっこ……出てる……♡」
やがておしっこは勢いを失い、おまんこ周辺を這うように濡らす。ぴゅる、ぴゅると最後まで出し切った頃には、おまんこはおしっこによってびしょびしょだった。
「……はぁ、気持ちよかった♡ あんっ、紙もぉ……っ」
俺はトイレットペーパーを回し、おしっこを拭き取るとぴくりと身体が反応してしまう。華凛の身体を動かしているという事実にも、俺はひどく興奮していた。
「はぁ……はぁ……あたし、学校なのにすごい興奮してるなー……はは」
紙をトイレに落とし、手を胸に宛てる。スポーツブラの綿の生地と中のウレタンのパッド越しに、柔らかいおっぱいが触れた。
「あっ……♡」
ばくばくと加速する心臓の鼓動と、緊張しっぱなしの手のひらは、おっぱいをぷるぷると震わせているようだった。熱い血を循環させられ、熱量も凄まじい。
揉むとおっぱいが形を変え、指先と手のひらに心地よさを伝えてくれる。
(俺っ……生徒のおっぱいに……ちょ、直接……っ!)
たまらず、俺はスポーツブラをずらす。ぽにょんとおっぱいが飛び出し、桜色の乳首が軌道を描いた。
(は……はは……俺に女の子のおっぱいが……あの華凛のおっぱいがついてる……)
乳輪の色はうすく直径も小さい、白い丘にちょこんと乳首が着いているようなおっぱいだった。
もっと触りたい。俺は包むようにおっぱいをすくい上げた。
「――でさー、今度その店行こうと思ってー」
「いいねー、いこいこ」
おっぱいを揉み始めると、突如女子トイレの中が騒がしくなってくる。女子の集団がやってきたようだ。
まずいか。声を出せないというのもあるが、女子のトイレは時間がかかるから開けないと迷惑をかけることになる。
(仕方がないか。また後で……楽しもう)
あの出席簿は何回でも使えるようだし、制約もなさそうだ。今はぐっとこらえ服を着直す。水を流して個室を出ると、トイレが開くのを待っていたようで入れ替わりで女子生徒が入っていった。
華凛と交流のない他クラスの生徒たちだったので、軽く会釈して手を洗ってから教室へと戻っていった。
机をくっつけていた來弥も元の配置に戻っていて、机に突っ伏している。俺も華凛のルーティンとして、仮眠をとることにした。
華凛として学校を歩き回ってみるのもいいが、普段の俺は学校をうろうろしているので会ったら元に戻ってしまう。別にまた出席簿に書けばいいが、刻下この時は華凛のままでいたかった。やるにしても、今日じゃなくていい。
「華凛ちゃん、5時限目体育だよー」
「んあー」
うつらうつらとしていると、來弥にぺちぺちと背中を叩かれる。
5時限目は体育か。時計もみると、そろそろ時間。あたしは着替えが入ったスポーツバッグを持って、來弥と一緒に女子更衣室に行き――着替えている女子生徒達を目の当たりにしたあたしは、場違い感を覚えた。
そこで――自分が華凛ではなく、華凛に乗り移っている男だと思い出した。
(そう……か。体育だもんな)
ここは、下着をちらつかせる女子生徒しかいない男子禁制の空間。まさか、俺が華凛になりすましているなんて夢にも思っていないだろう。現に、來弥もブラジャーを晒し、穿いていた黒いストッキングを脱いで丸めている。
來弥は俺に比べてかなりお子様体型で、ブラジャーもワイヤーが入っていないジュニアブラというやつだ。
「華凛ちゃん、あんまり見ないでよー。最近お菓子とか、たくさん食べてたからちょっとぷにぷにしてて」
「あはは、ごめんごめん」
「もー、恥ずかしいから華凛ちゃんもぷにぷにしちゃうもんねー」
「あ、ちょっと」
來弥はいたずらっぽく笑うと、俺のお腹をつまんでくる。俺は抵抗しながら、周りの女子生徒へも目を向けた。
運動部の生徒は俺と同じようなスポーティな下着だったり、垢抜けない顔つきでも黒の派手な下着だったり。華凛としても、他人の下着をじっくりと観察するのは初めてなので面白かった。
「來弥、時間なくなっちゃうよ」
俺はとめどなくじゃれついてくる來弥を制止し、來弥と隣り合ったロッカーに陣取った。二人して着替えを終えると、來弥と共に体育館に行った。
授業はバレーボール。華凛自身そこまで運動が好きではないので、積極的に運動はしない。熱中する男子たちや、はしゃぐ來弥を眺めながら、他のクラスメイトとのおしゃべりに時間を費やしていた。
「華凛ちゃん華凛ちゃん」
「ん? 來弥……あ」
「えーい!」
ふと話に割り込んできた來弥の方を見ると、ニコニコしながらバレーボールを投げつけてくる。それも割と強め。
しかし狙いは外れ、ボールは壁にぶつかり來弥の手元に戻る。
「うわー」
「逃げちゃだめだってばー」
俺は立ち上がって、あくまで楽しそうに投げてくる來弥から距離をとった。
その内心では女子高生同士として來弥とふざけ合うたび、自分は華凛という女子高生なんだと実感が募っていく。
華凛の私物を使い、女子トイレで用を足し、女子更衣室で着替えるという、華凛として過ごしていることに愉悦を覚えていた。
寒い体育館にあって、身体がじんじんと暖まってくる。
(……そろそろ、我慢できないかも)
華凛のおまんこが、俺の欲情に呼応して疼いていた。とろりと蜜を分泌しているのが、手にとるように分かる。
限界だ。來弥がコートに戻っていくのを見送った俺は、若い女性の体育教師にお腹を冷やしたと一声かけ、体育館から更衣室へと移動した。
更衣室は体育館から少し距離があり、授業中でもあるためしんと静まり返っている。授業時間が終わるまで、誰も来ることはないだろう。
「よし……」
どのみち今日は運動をするつもりはない。着替えてしまおうと思いロッカーを開けたが、そこは來弥が使っていたロッカーだった。俺のに比べて随分小さいブレザーから、一発で分かる。
「……」
ロッカーを閉じかけた手が止まる。
來弥は俺にとって……あたしにとって、高校で一番の友人。入学式の日から、見た目を気にしないで話しかけてくれた。ちょっとSっ気があるけど、優しい子。
あたしが、華凛がそう気づいていないだけで、來弥に抱いているのは友情とは異質な気がしてきた。
「……今ならバレないよな」
自然と俺の手は、來弥のバッグへ伸びていく。來弥のスポーツバッグを開くと、制汗剤やシャツ、丸められたストッキングなどの他に、淡い桃色の下着。
「はぁ……はぁ」
いけないと思いつつ、あたしは來弥の下着を広げる。
チュールレースでふんわりと彩られた、ショーツとブラジャー。さっき身につけていたシンプルな下着とは違った意味で子供っぽく、來弥らしい。
鼻に押し当ててみると、すずらんの柔軟剤の香りに混じって、來弥の匂い。何度か遊びに行った時、來弥の部屋に充満していた來弥の甘い匂いがした。
「あっ……來弥、來弥♡」
あたしのお腹の中がきゅんきゅんと唸る。あたしが保っていた理性は、介在した俺の思念によってぷっつりと切られてしまった。
すぐ裸になったあたしは、來弥のショーツに脚を入れる。サイズが違うからちょっとお尻はきついけど、ポリエステルのつるつるとした素材が素肌に心地よかった。
続いて、ブラジャーのストラップを肩に通す。ホックは一番大きいところなら大丈夫だったけど、カップは少し小さいみたい。ハーフカップってのもあって、谷間が強調される形になった。
「はは……來弥の下着、着けちゃった……」
女子同士でも、下着の貸し借りなんてしない。それなのに、あたしは來弥が着替えに持ってきてる下着を着けてしまっていた。
どくんどくんと、心臓が早鐘を打っていく。
來弥がおっぱいを入れていたところにあたしのおっぱいが収まっているし、來弥の……おまんこが触れて、おりものやおしっこを染み込ませていたクロッチが、あたしのおまんこをぴったりと包み込んでいる。
「あ……あぁ……♡」
あたしってこんな、変態みたいな子だったっけ――そう内省すると、あたしが感じていた悦びから、隅に隠れていた"俺"が異を唱える。
そうだ、すべては俺のせい。あの出席簿は、乗り移った人間の記憶や思考にも影響を与えると書いてあった。
おそらくは俺の感情を、華凛の思考が來弥への想いを屈折させ、友情を超えた憧れとして解釈しているのだろう。
ということは、俺が身体から抜け出た後も華凛はこの想いを引きずることになるのか。
「ふふっ……」
しかし、この後のことなんかどうでもいい。俺の道徳もだいぶ麻痺しているのを自覚していたが、些末なこと。
親友をオカズにしてしまう変態女に仕立て上げ、その甘く切ない気持ちを享受したいだけだった。
俺は來弥のバッグで丸められていた黒のパンティストッキングをほどく。やや厚手の生地はしっとりと汗を吸っていたようで、下着よりも強く來弥の体臭がした。
「すぅ……來弥、來弥……♡」
十分に満喫したら、パンストを顔から離し、脚を差し込んでいく。これも華凛の経験はあるが、男としてはぴっちりと脚に貼り付いていく感触が奇妙だった。
「ちょっと……引っかかる……」
気化熱の作用だろうか、既に汗ばんでいたからかパンストは穿いた途端に冷たくなっていく。最後まで引き上げ、ガニ股になって調整も済ませてしまった。
「もっと……」
熱に浮かされたように、俺は來弥のTシャツ、ブラウス、そしてブレザーと着込んでいく。一回りほど小さく、袖は若干足りないしスカートも短い。
「來弥の制服……着ちゃった……♡」
もう、股間はいけないことになっている。とろとろと愛液を垂らし、ショーツを濡らしているのが分かった。
これ以上はまずい、來弥にバレたら嫌われてしまう。あたしは恐れつつも、全く歯止めが効かなかった。
「んっ……あぅ……♡」
スカートの中に手を差し入れパンストとショーツ越しに、ダイヤマチで囲われたデリケートゾーンをこする。僅かに欠けている爪がひっかかり、かりかりと音を立てる。それは緩急となって、俺を苛んだ。
さらに、あたしはおっぱいを揉む。女子高生としてはそこそこのサイズのおっぱいだが、小さいブラに締め付けられ柔らかさはあまり感じられないし、刺激そのものは弱い。
けれども、來弥の服を脱ぎたくはない。股間だってそう。もっともっと、気持ちよくなりたがっているけど、ショーツだってパンストだって脱ぎたくない。
來弥のなんだから、脱がないほうがいいに決まってる。
「やぁ……っ、來弥ぃ……っ♡」
あたしは両手をパンストから差し込んで、直接おまんこをいじる。
もうびしょびしょで、來弥のショーツもパンストも大変なことになっていた。でもあたしは構わない。一心不乱にクリトリスをこね、入り口の周りにあるびらびらを撫で回した。
「あっ、あっ、ああぁっ♡」
あたしは今、下着まで來弥の服を着てオナニーしてる。しかもいつ誰がくるともしれない、学校の更衣室で。狭い室内にくちゅくちゅというおまんこの水音と、情けない喘ぎ声を響かせているなんて、來弥が知ったら軽蔑するに違いない。
しかも――"俺"がそうさせていること。華凛のすべてを支配した俺が、彼女の想いを捻じ曲げ、來弥との友情を踏みにじって、俺の快感だけを追求させる。生意気な生徒を屈服させているようで、最高に気分が良かった。
そう認識した瞬間、俺の快感は弾けとんだ。
「あぁっ、やだ、だめぇええええっ♡ イく、イくぅうううぅ♡」
心も身体も歓喜の音を奏で、視界が明滅する。俺はその場にへたり込む。俺を包んでいた來弥の匂いは、あたしの雌臭さと混じり合っていった。
「……はぁ……はぁ……はぁ……」
気だるさと余韻に浸っていると、つうとよだれが來弥のジャケットに垂れてシミを作る。
「いけない……」
思考がまともになってくると、ひどい有様だと後悔した。制服やブラジャーはまだいい。俺の愛液まみれにしてしまったショーツとパンストは、言い訳などできない。この場を誤魔化すことはできるかもしれないが、やがて問題になる。
なにより、來弥が知ったらどんな顔をするか。あたしは、考えたくもなかった。
俺としては來弥と華凛がどうなろうと知ったこっちゃないが、乗りかかった船だ。
「……となると」
手段はひとつだけ。華凛と來弥、二人の記憶と感情を改編するしかない。学校でも仲良しの、いつしか深い仲になっていたと過去を作り上げてやる。
俺は、即興の筋書きで強く自己暗示をしていく。
あたし――華凛は、來弥と恋人。女の子同士だけど、前に來弥をあたしの家に泊めた時、來弥がくすぐってきて……それで感じちゃった。
それが來弥の嗜虐心に火を付けたみたいで、ファーストキスを交換して、結局最後までした。それからというもの、お泊り会のたび、いっつも朝まで……。
最近はなかったから、もっと來弥を感じたくて感じたくて、ちょっと暴走しちゃった。
――こんなところか。來弥は好きな子に意地悪しちゃうタイプの人間とみえる。華凛も來弥のことが大好きだ。じゃれあっているうち、お互い燃え上がっていった……という流れなら自然か。
「そしたら……やば、時間」
華凛の"洗脳"を終え時計を見ると、授業の終わりまで10分もない。急いで來弥の服を全部脱いで、華凛の服に着替え直す。
「えーっと……てことは、俺のところか」
俺はスカートを翻して、生徒指導室へ走った。ノックもせずにドアを開くと、一瞬だけ俺の姿が見えて――カメラが切り替わるように、視点が変わった。
中央に捉えていたのは、赤い顔で息を切らす華凛の姿だった。書類仕事をしていた俺は、前触れのない闖入者に驚くふりをしつつ問いかける。
「……ど、どうした?」
「え……どうしてだろ……はぁ……はぁ……」
「……疲れているのか? じゃあ、今日は帰って寝ていいぞ」
「え? ああ……そう……する」
反応をみるに、俺が乗り移っていた事実などは記憶になさそうだ。本当に、なぜここに来たのか判らないといった様子のまま、華凛は立ち去っていった。
「ふぅ……っと、まだこっからだ」
脇に置いてあった出席簿を開き、今度は『2-D 緒方 來弥』と名前を書く。
すると、気が遠くなり――俺は、女子更衣室のドアに手をかけていた來弥に憑依していた。
「……っと」
視点が一気に低くなり、つまずきそうになる。華凛はまだしも來弥は145cmしかなく、元の俺と比べて約30cmも差があった。
俺は歩幅を整えて、自分の――來弥のロッカーを開く。さっき華凛として適当に服を突っ込んだため、來弥の記憶とは明らかに様相が違っていて、荒らされたかのようだった。
來弥の気持ちとしては、戸惑いが最初に来た。どうして? 誰が? と。これが仮に華凛の仕業で、わたしに黙って服を着て厭らしいことをしていたとしたら――想像しようとしてみたが、華凛ちゃんは絶対そんなことしない、とブロックされてしまうようだった。
すかさず、來弥の記憶を改ざんする。
わたしは、ちょっとだけ早めに更衣室に到着していたんだけど、ちらっと覗いたら華凛ちゃんがわたしのお洋服を着てえっちなことしてたの。
お家ならさ、いっつもお泊りのときいっぱいしてるんだけど、学校であんなことをするなんて。確かに、最近エッチしてなかったな。ふふ、じゃあ今日は学校でしてあげよっかな。華凛ちゃん、嫌がるかな。嫌がる華凛ちゃん、見たいな。
――こんなところか。來弥は好きな人に意地悪したくなっちゃう、ちょっとSな性格。ベッドの上では主導権をとり、華凛にたくさんおねだりさせている……ということになった模様。
今日の放課後も、これをネタに遊んであげるところまで來弥の思考が描かれたのだった。
俺はいったん來弥の思考を置いておき、着替えを始めた。タオルで汗を拭いて、制汗剤を噴きつけると、下着も脱いでしまう。
(……やっぱりお子様だな)
更衣室の隅にある姿見を覗きこむと、それなりに女性らしいといえた華凛とは違って、來弥はとても高校生には見えない。凹凸の少ない体つきとあどけない顔は、小学生に混じっていても少し成長のいい子どもぐらいだろう。おまんこもぴったりと閉じていて、毛も生えていなかった。
あまり趣味ではないが、元の身体とはギャップが楽しめそうだ。期待に顔を緩めると、ぽんと背中が叩かれた。少し息を切らしている華凛だ。
「やほ、來弥」
「あー華凛ちゃん! どこ行ってたのー?」
「あはは、ちょっとお腹痛くて。でももう大丈夫」
華凛はごく普通の調子で言う。さっき、來弥の衣類でオナニーに及んだ罪悪感などはないようだった。これは気づかれないと油断しているのか、そもそも後ろめたさなどないのか。華凛の身体を抜け出ているので、思考が読めない。
俺は、真意を確かめるために直接ぶつけることにした。
「ねー華凛ちゃん、これ! さっき見たよ、へんなことしてるの」
俺は頬を膨らませながら、濡れたショーツのクロッチを拡げた。
「あー……見られてた?」
「もー……したいなら言ってってば。じゃあ、今日の放課後ちゃんとしてあげるからさー」
「ごめんごめん、なんか急にムラっときちゃって」
平静に会話をしながらも、俺は心の中で笑い転げていた。
華凛は、二人はずっと昔からレズセックスをする間柄だという先程植え付けた偽りの記憶を信じて疑っていない。頭の中では來弥もそうだと錯覚している反応が流れ続けている。
「時間なくなるよ。來弥も着替えな」
「はーい……あ、べとべとしてるー……」
來弥が着替えとして容易していたふわふわレースのショーツと、朝から穿いてきていた黒いパンストはまだ濡れていたが、気にせず身につけた。
華凜の愛液と汗でべったりのそれらは、來弥が体育で流した汗よりすごい。股間だけ色が変わっているほどだし、おもらししたようにしか見えなかった。
俺は着替えを終え顔を上げると、他の生徒がほとんど残っていない中、華凛がのぼせた顔で見下ろしていた。
「むー……なにさー」
「いや……なんかあたしが汚したの穿いてるなって思うと、また……」
「華凛ちゃんのえっち……」
非難するように口を尖らせつつも、ひんやりと冷える股間に俺の――わたしの子宮も熱くなってきていた。
ここしばらくエッチをしていないのは、わたしも同じ。華凛ちゃんがひとりで勝手に発情して、あまつさえわたしの服で事に及んだのは、ずるいという思いでいっぱいだった。
そんなところに、華凛ちゃんの愛液や汗が染み付いたショーツやパンストを穿いたら……わたしだって、えっちな気分になっちゃうよ。
わたしは華凛ちゃんに顔を近づけて、甘え声で囁く。
「ねえ……えっち、しよ?」
「え……でも」
「体調悪いって嘘ついたんでしょ? 次の授業自習だし、わたしたちなら居なくたって付き添いだって思われるでしょ。それに」
「んっ……こら」
わたしは華凛ちゃんのスカートに手を入れて、ショーツ越しにおまんこをつつく。さっきまでたくさんオナニーをしていた華凛ちゃんの体はまだ冷めきってなくて、わたしの顔を華凛の息が撫ぜる。
「華凛ちゃんだけ、ずるいんだもん」
「はぁ、はぁ……來弥、駄目だよ……」
「だめじゃない。ほら、まだ華凛ちゃんのおまんこはほしいよーってうねうねしてるし、クリちゃんもまだまだ元気だって」
「ひぁっ……あん♡」
ショーツの隙間から華凛ちゃんのおまんこに指先を入れたあと、クリトリスをくにゅりとつまむ。華凛ちゃんは目を閉じ、声を出さないよう必死に我慢していた。
他のクラスメイトも見てはいたけれども、いつものじゃれあいだと気に留めず、みんなさっさと出ていってしまう。
次の時限はどのクラスでも体育の授業がないから、誰も来ない。まもなく、女子更衣室はわたしと華凛ちゃんだけになった。
静かになった部屋は、漏れ出す華凛ちゃんの喘ぎ声と、くちゅくちゅといやらしく響く水音が独占した。
「ねえ……みんないなくなったよ。まだ、やなの? もうひとりで発散したから、我慢できるの? わたしには我慢させるの?」
「んぁっ、く、來弥……」
「ふーん……じゃあいいや。また今度にしよっか。嫌ならしょうがないもんね」
「あっ」
「ほら、華凛ちゃんのだよ。綺麗にしてね」
おまんこから抜いたわたしの指を華凛ちゃんの口へと運ぶと、猫のようにぺろぺろと舐め取ってくれる。
「じゃあ、教室戻ろっか」
「……」
そう言ってわたしは歩を進めようとしたが、スカートが引っ張られた。振り向くと、華凛が潤んだ瞳でこちらを見つめている。
そうだよね。華凛ちゃんなら、そうするよね。
「……やだ」
「どうしたの? 華凛ちゃん? なにがやなの?」
「しよ?」
「なにを? ちゃんと言わなきゃわかんないよ?」
「……もう、えっちに決まってるじゃない」
華凛ちゃんは、か細い声を絞り出す。
――かわいい。わたしがちょっかい出しても反応薄いのに、突き放すとすがってくるところ。いっぱいして欲しいのに、素直じゃないんだよね、華凛ちゃん。
わたしは――俺は、華凛への愛おしさが溢れ出ていく來弥の気持ちに飲み込まれそうになってしまったが、我に返った。
少し危なかったな。感情や記憶の過度な干渉は、俺の精神にも悪影響を及ぼすようだ。
……にしても、凄まじい。俺はさっきまで自分を來弥だと、華凛の親友にして恋人の女の子だと思い込んでしまっていた。そこに、俺という成人男性の感情はなかった。
「……來弥……ねえ」
俺は少し冷静になったが、眼前では相変わらず華凛が待てを命じられた子犬のように震えながら見下ろしてきていた。
よし。あまり溶け合わないよう気を付けながら――華凛と來弥の百合エッチを楽しませて貰うとするか。
「うん……よく言えました」
俺は不意に笑みがこぼれる。華凛には優しげに見えただろうが、その実、ここまで二人を思うようにできたのだという昏い愉悦からくるものだった。
俺は少し背伸びをして、華凛に口づけをする。柔らかく温かい、華凛の唇が触れ合った。
「ん……」
華凛は少し膝を折って、俺に合わせてくれる。それが嬉しく、キスにも熱が入っていく。
「んっ……く、來弥……」
舌を吸い、内側から華凛の頬を舐める。僅かに苦しそうな声を出していたが、逃さない。顎にまでよだれが垂れるほど長いキスをしてから、ようやく離してやった。
「はぁ……なんだか、とってもドキドキするね」
「あたしも。なんだか、初めて來弥とキスしたみたい」
実際、初めてだろうからな。記憶は書き換えたが、経験では少しほころびがあるのかもしれない。
俺も、身体がじんじんしてたまらなかった。おそらくは、さっき華凛も口にしたように、來弥の肉体も華凛とのキスに慣れていないのだろう。
「ねえ……華凛ちゃん。華凛ちゃんはもう気持ちよくなっていたんでしょ? 先に……わたしを気持ちよくして」
俺はスツールベンチに仰向けに転がって、M字に脚を開く。パンストとショーツをずらすと、泡立つほど濡れたおまんこを華凛に見せつけた。
「いつもどおりに……ね?」
「いつも……どうやってるっけ」
「忘れちゃったの? ワンちゃんみたいに、わたしのおまんこぺろぺろしてくれたよね?」
俺は白々しく答える。忘れたのではなく、そんな過去などなかったのに。華凛もどこか腑に落ちていないようだったが、それでもおずおずと舌を伸ばしてきた。
「あっ……あぁん……」
俺の脚の間に華凛の頭が入り、俺のお子様おまんこへとおいしそうに舌を這わせる。なめくじのようにぬめった舌は、華凛でオナニーしたときより数倍の快感を生み出してくれた。
「ひぅっ……あぁん……やぁ♡」
「っぷ……來弥、これでいい?」
「うん……いいよ」
「じゃ、じゃあ今度は上もやってあげるね」
華凛は、俺の上半身に着ていたものを脱がせていく。ふわふわな淡い桃色のブラジャーも外すと、俺のちっちゃな乳首を口に含んだ。
「ひっ……♡」
華凛は手で俺のおまんこを愛撫しつつ、舌先で平らなおっぱいにちょこんとついた乳首を転がす。
しかし、いずれもぎこちない。迷っているような、探り探りな動きだ。それは、華凛が女の子とのセックスなどしたことがないからだ。逆に考えると、華凛にとってこうすれば一番相手が悦ぶと思っている行為に他ならない。
……このまま経験のないペッティングを強要したら、全てウソだったと感づいてしまうのだろうか。
もう、クライマックスといこうか。華凛ともっと深く愛し合いたい來弥の情欲に、また飲まれてしまいそうなこともある。
「華凛ちゃんも気持ちよくなろ……華凛ちゃんも下、脱いで」
「……うん」
華凛の手から抜け出ると、俺と華凛は下半身の衣類をすべて取り払う。こうして比べると、華凛のおまんこは來弥より明らかに愛液の分泌量が多い。というか、俺もかなり興奮しているのにほとんど愛液は出ていなかった。
もっとも理由なんて今はどうでもいい。俺は華凛をスツールベンチに寝かせると、二人のおまんこ同士をすり合わせるよう脚を絡める。
「あそこ……くっつけちゃったね。じゃあ……あんっ♡」
「あっ、ああぁん♡」
数秒見つめ合ったあと、腰を動かし始める。
肉体的な刺激ではない。愛する人と女の子の一番大切なところをぴったりと密着させている事実に、俺の中の來弥が狂おしいほど喜んでいる。
大陰唇がこすれ、クリトリスがぶつかり、太ももやお尻がぺちぺちと音を出す。
「ひあぁん、華凛ちゃん、華凛ちゃんっ……♡」
「來弥ぃ……♡」
名を呼びあうと、快感はさらに高まっていく。
男女のようにつながると言い表すこともできない、重ねているだけのおまんこなのに、快感は表面だけに留まらない。俺の未熟なおまんこの中へ中へと、痺れが忍び込んでいくようだった。
そして、その痺れは子宮にまで到達する。手足の末端の感覚はほとんどなく、視界がちかちかと瞬いてきた。
華凛のときとは少し反応が違うが、來弥もイきそうになっているみたいだ。
「ひぃっ、あっ、華凛ちゃん、わたしイっちゃう♡」
「あ、あたしもぉっ♡ イく♡ 一緒にぃ、イこ♡」
わたしとのレズセックスで、華凛ちゃんもイきそうになっている。それはわたしにとってなにより嬉しく、最高の幸せだった。
そして――決壊する。
「あぁぁあっ、イくっ、あああああぁん、やああああぁぁぁっ♡♡♡」
「來弥、くるみぃいいぃいっ♡♡♡」
身体がびくんびくんと震え、二人の間に熱い液体が飛び交う。お腹の中が、子宮が猛烈に歓喜して全身へと快感を送り出していった。華凛ちゃんと一緒にイけた――わたしはもう死んでもいいほどめちゃめちゃに嬉しくて、身体から力が抜けていった。
「はぁ……はぁ……來弥」
「えへへ……」
あれからどれくらい経ったかな。
華凛ちゃんと重ねていたおまんこを離し、力なく抱き合う。身も心もふわふわとしていて、夢のようだった。
「なんだか……來弥と初めてした時みたい」
「学校だから、かな」
「そうかも」
わたしたちはふふっと笑い合う。
ここまできたら、もう華凛も催眠だったなどとは気が付かないだろう。來弥にも、快感と鮮烈な体験を深く刻み込んだ。これで、二人はもう離れられない。
「じゃあ……教室戻ろっか」
「……うん」
俺たちは服を着ると、痕跡も綺麗にして更衣室の扉を開く。
廊下の遠くに人影が見え、近づいてきていた。わたしより目がいい華凛は、小さく呟いた。
「あ、藤沢じゃん」
「生徒指導のか。あれ……」
生徒指導の担当の、藤沢。そこまでわたしとは接点がないはずなのに、なぜかとても懐かしく――
トイレに行こうとしていた俺は、廊下で腕を絡ませる女子生徒二人を発見していたのだった。
――元に……戻ったのか。全身を包んでいた幸福感は消え去り、とてつもない寂寞感に襲われてしまう。
俺はふうと深呼吸してから、口を開いた。
「……ああ、華凛が体調悪いとさっきすれ違った生徒が話していたが……來弥も付き添っていたのか」
「はい。華凛ちゃんを放っておけなくて……」
「無理はするなよ」
「はーい」
肩をなでおろす二人とすれ違った後、俺はトイレで小便を済ませる。俺が華凛や來弥になったのは、全て合わせてもせいぜい一時間と少しの出来事だったはずなのに、自分にチンポが生えているのに違和感を覚えた。
自席に戻った俺は例の出席簿を開くと、來弥の欄に出席を意味する丸が付けられていた。
「はぁ……」
急に、俺の人生がつまらなく感じられてきた。俺にも数年付き合っている恋人はいるし、お互い結婚を意識している。だが、あそこまで燃え上がるようなセックスはしたことがないし、きっとこれからもその機会は訪れない。
はっきり言って、華凛や來弥が羨ましい。
「……」
俺は、もう一度出席簿を開いた。
冬休み開始の前日、終業式。俺は列に並んで、ぼんやりと教師たちの話を聞いていた。
校長先生の取るに足らない話、生徒会長の身にならない話、そして生徒指導担当の藤沢――元の俺からの、私生活についての話。
(これだけ距離があれば戻らないんだな……)
真面目にやってるんだな、とどこか他人ごとのように聞き流す。
不思議なことに、出席簿のページも自動で補充されて切れることはない。そのため、あれから元の俺として過ごした時間はほとんどない。大抵は華凛か來弥になって暮らしていた。
出席簿というだけあって、うちの生徒以外には乗り移れないのだが、それに文句を言うのは贅沢か。たまに気分で二人以外の女子生徒も試したりはするが、結局は戻ってくる。
終業式が終わると、生徒たちは順繰りに体育館から捌けていく。その途中、俺達はおしゃべりをしていた。
「華凛ちゃん華凛ちゃん、冬休みだね。いっぱいいっぱい、遊ぼ?」
「そうだね、來弥」
俺たちは手を絡め、やけに近い距離で歩いていく。
冬休みに入れば、しばらく藤沢と会うこともない。俺はその間、女の子でいられる――そう思うと、ほころぶ顔と唸るおまんこを抑えられなかった。
[おわり]